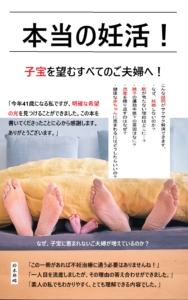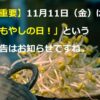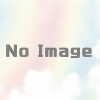記憶力を前提にすれば、子どもの学力を上げることと認知症の改善策は同じ手立てです!
「塾にも通い、家庭教師までつけているのに…」
子どもの学力向上を願い、多くのご家庭では教育費に力を入れているようです。が…
その裏で、(知らず知らずのうちに)子どもの脳の働きを悪くする食べ物を与えていることをご存じでしょうか?また、その食べ物は私たちの将来における認知症リスクを上昇させます。
単純に、認知症→記憶力低下です。記憶力が低下すればするほど、勉強がはかどらなくなるのも自然なこと。では、まずは認知症とはどんなものなのか?から、確認していきましょう。
【お願い】
今回の記事は〝あえて″まとまりがない形で話を進めています。これら点と点を、線で繋げて自分の頭で考えてみましょう。
認知症とは?
「認知症 ニューロン」とGoogleで検索すると次のような解説が表示されます。
ここで神経細胞(ニューロン)にまつわる常識を再確認しておきましょう。
例えば、私はここ数年前から思い出せなくなっている漢字が増えていることに氣づきました。これは節約の法則と呼ばれ、脳は使わない領域のニューロンの結びつきが弱くなることが原因とされています。
同じことは計算でも起こります。足し算や引き算、掛け算など、若い頃はカンタンにできたのに、だんだん計算するの遅くなりますよね。これも、使わないから、節約の法則が原因です。
脳の老化の常識
人間の脳は老化すればするほど神経細胞が死んでいく。
私たちはそう教えられてきましたが、果たしてこれは本当のことなのでしょうか?
これまで脳の老化は,神経細胞(ニューロン)の消滅が主な原因であると思われてきた.
一説には「脳の神経細胞は一日に10万個死んでいる」とも言われてきたが,この通説を裏づけるデータは実際のところ見当たらない.
・食品成分による脳老化改善・認知症予防の可能性 久恒 辰博 2016年 54 巻 12 号 892-900 より引用
少し話は反れますが、ウイルスの話を前提にすればこれも「脳の老化」の話もウソかもしれませんね。
実は、ウイルスは存在しません。
その典型はインフルエンザで、あれほど毎年流行るのに、ただの一度もインフルエンザウイルスは確認されたことがありません。これは事実です。
存在しないウイルスが〝いる!″という前提でウイルス学は成立しているのが現状ですよ。
認知症予防に効果的なのは?
地中海食は認知症予防に効果的である一方で、肉や乳製品は控えた方が賢明である。これは、疫学調査で明らかです。
大規模な疫学研究を通じて,日常的な食事パターンと認知機能維持との関係についての研究も進められている.
米国のコロンビア大学の研究グループなどが中心となって,魚介類の摂取など地中海的な食事パターン「地中海ダイエット」が認知症予防に対して効果的であることが示された.
地中海ダイエットの特徴としては,欧米人において摂取量が多い食品群である牛乳・乳製品ならびに畜肉(牛肉と豚肉)については,その摂取量が低いほうがよいとする点が挙げられる.
・食品成分による脳老化改善・認知症予防の可能性 久恒 辰博 2016年 54 巻 12 号 892-900 より引用
学力が上がらない。記憶力が悪い。
そんなお子さんの食事ですが、魚食と肉食の割合はどうでしょうか?
また、1週間における魚介類の消費量と肉や乳製品の消費量を比較するとどうなりますか?
おそらく、ほとんどのご家庭では肉量:魚量=9:1~4:1と、圧倒的に肉を食べていることでしょう。ならば、この疫学調査結果をどう捉えますか?
※ 疫学調査:集団を対象として、病気の頻度、その分布に影響する因子を統計学的に研究する学問のこと
参考までに、肉や乳製品などの高脂肪食の摂取は高血圧を誘導し、腸内で酪酸が減少します。
高脂肪食を投 与 す る こ と で 高 血 圧 が 誘 導 で き て, 菌 叢 がFirmicutes 優位に変化し,短鎖脂肪酸(short-chainfatty acid:SCFA)の酪酸が減少することが報告された.
そのラットの腸内細菌を同条件の普通食投与の非高血圧ラットに移植すると高血圧になることも示されている.
・腸内細菌叢と心血管病 山下 智也, 平田 健一 2017年 53 巻 11 号 1073-1076 より引用
腸内の酪酸減少は妊娠の鍵を握る物質、制御性T細胞の減少を招きます。事実として、酪酸が減少すればするほど、受精卵の着床率低下や流産率、早産率が上昇します。
ぶっちゃけ、肉や乳製品の積極的な摂取が不妊に繋がるという話ですね。
もし、不妊で悩む方がいらしたら「本当の妊活!」をお役立てください。
脳の神経細胞(ニューロン)は再生する!
脳の神経細胞(ニューロン)は老化に伴い死んでいき、どんどん減少する。一度死んだ神経細胞は元には戻らない。
私たちはそう教えられてきましたが、どうやらこれもウソだったようです。
ニューロンの新生に関する研究は1990年代から再度発展をし、生後減る一方であるといわれ続けてきたニューロンが高齢者の脳で新生することが確認されてきた。
・子ども虐待の現状と再生医療 大草 亘孝, 中井 真理子 2024年 22 巻 1 号 11-18 より引用
ヒトを含む哺乳動物の成体脳には、未分化なニューロン前駆細胞が存在し、限られた領域ではあるが、絶えずニューロンの新生が起きている。(中略)
ニューロン新生は海馬歯状回においても活発に起こっており、
・『神経系再構築とミクログリア』 ニューロン変性後に活性化するニューロン新生シグナル―ミクログリアの関与― 米山 雅紀, 荻田 喜代一 2013年 142 巻 1 号 17-21 より引用
※ 成体:子を産みふやすことができるほど十分に発育した動物
☑ 高齢者の脳であっても、神経細胞(ニューロン)は再生する
☑ 学習と記憶に重要な脳の部位である海馬歯状回においても、ニューロン新生は活発である
この事実を前提にすれば、私たちが何らかの形で神経細胞(ニューロン)の再生(新生)を妨げているからこそ認知症に至ることが想像できます。
また、海馬歯状回でニューロン新生が活発であるからこそ、その再生(新生)を妨げることが記憶力を大きく低下させることも容易に想像できることでしょう。
炎症が神経細胞(ニューロン)の新生を阻害している!
私たちは知らないことだらけです。学ぶことに終わりはありませんから、正直何気ない毎日でも知るべきことはたくさんあります。また、年を経ているからこその氣づきも山のようにあるのも事実です。
高齢者の脳であっても、学習と記憶の部位である海馬歯状回でニューロン新生が活発であるのはそのためでもあるのでしょう。
では、何が脳のニューロン新生を妨げているのでしょうか?
高齢のサルでは学習・記憶機能が若齢のサルに比べると低下していた.
ニューロン新生に関して,その源となる神経幹細胞の数は比較的保たれているものの,新生ニューロンに至る細胞分化が顕著に阻害されていること,この阻害に脳組織内に生じる炎症性の反応が関与していることが示唆された.
・食品成分による脳老化改善・認知症予防の可能性 久恒 辰博 2016年 54 巻 12 号 892-900
上記論文の通り、神経幹細胞が分化して新生ニューロンに至ります。また、高齢でも真剣肝細胞数は保たれているようです。ですが脳組織内に炎症が生じると、新生ニューロンへの分化が阻害されています。
逆に、炎症が静まれば以下の通り新生ニューロン数は増加し、記憶力は保証されます。
高齢の動物におけるニューロン新生の程度は個体差が際立って大きく,新生ニューロンの数が多い動物ほど記憶機能が高い傾向にあった.
この現象の説明として新生ニューロンの数が多いために記憶機能が高く保たれていると考えることもできなくはないが,それよりはむしろ,記憶能力が高い高齢動物では脳の炎症反応が比較的抑えられていて,その結果として新生ニューロンの細胞分化が保たれていると考えるほうが,現在では主流である.
・食品成分による脳老化改善・認知症予防の可能性 久恒 辰博 2016年 54 巻 12 号 892-900
子どもの記憶力も同じだと思いませんか?
脳に炎症が生じるような食事を摂っているなら?子どもの学力が上がらないのはそのせいかもしれませんよ。
千島学説を思い出しましょう!
ここで千島学説を思い出してください。(知らない方は以下の記事、もしくはブログ検索で「千島学説」と入力して記事をお読みください。)
・【拡散希望!】ワクチン打っても食事を改善すれば助かるかもしれません!すべては赤血球の質です
・子どもを授かる前の女性に伝えたいこと!現代の「油断大敵」に氣づかない人生は悲惨!
【重要】千島学説
私たちが食べた物が小腸の絨毛で赤血球となる。→その赤血球が白血球へ分化(変化)する→その白血球がたどり着いた先の臓器細胞へ分化(変化する)
この千島喜久雄先生の発見より、食事が脳における炎症の原因に成り得ることが想像できます。
では、どんな食事が神経幹細胞の分化にどのような影響を与えるのか?確認してみましょう。
必須脂肪酸(オメガ6とオメガ3)が神経幹細胞分化に与える影響!
当社のメルマガ購読者でも、未だ頻繁にサラダ油を使う「炒める」「揚げる」というご家庭が少なからずいらっしゃるようです。
ですが、再三指摘している通りサラダ油や大豆油、コーン油など食用油にはリノール酸(オメガ6)が豊富です。また、これら食用油を使う調理の主役は肉や乳製品といった高脂肪食でもあります。したがって、千島学説の指摘によると、食用油で調理された食事からオメガ6が豊富に含まれた赤血球が生じます。すると…
我々は、このようなn-6 PUFA過多/n-3 PUFA欠乏という食事様式が脳形成に与える影響を解析するため、妊娠マウスにn-6 PUFA過多/n-3PUFA欠乏飼料を与え、その仔マウスの大脳新皮質を解析した。
n-6 PUFA過多/n-3 PUFA欠乏飼料を摂取した母マウス由来の胎仔脳において、大脳新皮質の厚さの減少が認められた。
このとき、脳を構成する様々な細胞を生み出す神経幹細胞の数に群間差は見られず、実際に脳機能を担う神経細胞(ニューロン)の数が減少していた。また、新生仔マウスの大脳新皮質においてもニューロン数の減少が確認された。
・健やかな脳の発生・発達と脂質 酒寄 信幸, 大隅 典子 2016年 21 巻 4 号 4_59-4_62 より引用
上記論文の通り、オメガ6が過剰な食事は神経細胞(ニューロン)の減少に繋がります。
また、オメガ6は「炎症を促す」生理活性物質を生じます。よって、オメガ6を豊富に取り込んだ赤血球が神経幹細胞に分化すれば、その神経幹細胞に炎症が生じるのは自然なことでしょう。
これらより、オメガ6過剰かつオメガ3欠乏食を食べると、記憶と学習に重要な領域である海馬歯状回のニューロン新生が妨げられることが想像できます。
この事実は「本当の妊活!」にも記しましたが、上記の通り妊娠期に母がオメガ6過剰な食事を摂れば胎児のニューロン数が減少します。その結果が子どもの学習障害や発達障害であると考えるのは、果たして私だけでしょうか?
まとめ
認知症を発症したヒトの多くは、感情の起伏が激しくなる傾向があります。
また、学習に問題を抱えた子どもも、乱暴な物言いやキレやすい、集中力がない、ゲーム依存といった傾向を併せ持ちます。
私は、これらの問題解決に10日間チャレンジという習慣をご紹介していますが、以下のような研究結果も併せてご確認ください。
久司道夫によるマクロビオティックな給食にしたことでスペインの刑務所での凶暴性が減ったことや,大塚貢による長野県の荒れた中学校を和食給食で立て直した
・病気にならない生活 ―どういう食生活が健康長寿をもたらすか?― 渡邊 昌 2019年 17 巻 1 号 63-74
オメガ6が過剰な食事を摂れば摂るほど、そのヒトの感情は乱れることになるのです。
ならば、学習や記憶力低下も頷ける話ですよね。