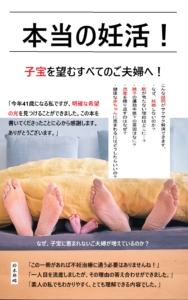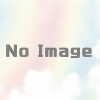「本当の妊活!」第一章の1見出しをご確認ください。専門家は、不妊の原因を知っていますが…
重要な事実をご紹介しておきます。
専門家は、不妊が激増している原因を知っています。知っていますが、その原因を‶正確に〟指摘しているヒトを私は知りません。つまり、原因を無視して「不妊治療」が行われています。
例えば、真夏にストーブを焚きながらクーラーをかけても意味がありませんが、妊娠できない原因を排除せずに不妊治療を行っても意味はありません。でも、日本の不妊治療の現実はまさしくこの状況です。
「本当の妊活!」第一章 常識にとらわれているから子宝に恵まれない!
・乳牛と肉牛の受胎率が違う!という事実から得られる教訓とは?
「3人目も男だったら…、そう思うととても…」
これ、私の母の口癖でした。両親とも女の子を夢見ていたそうですが、とんでもなく落ち着きがない二人の息子という現実に夫婦で話し合いあきらめたそうです。そんな私の両親のような夫婦が羨むであろうことが、牛の人工授精で可能なようです。
そう、牛は90%以上の確率で雄雌の産み分けができるようになっています。
牛の妊娠はほぼ100%が人工授精です。その際、Ⅹ精子(雌)とY精子(雄)を90%以上の正確度で選別できる技術が開発され、雄雌の産み分けが可能になりました。そんな技術の開発理由も容易に想像できますよね。
牛乳を搾れるのは雌牛です。雄牛が生まれても困ります。また、肉牛は体格の良い雄牛が適しているそうです。畜産業も経営がたいへんですから、産み分け技術の進歩は生産現場にとって切実だったのでしょう。
そんな産み分け技術が進歩しているにも関わらず、畜産業では牛の不妊が深刻な問題となっています。まるで、日本人の少子化と歩みを共にするかのように…。
その様子は次ページのグラフで確認できますが、その前に同じ不妊でもヒトと牛の違いを確認しておきましょう。
ヒトの場合、女性に原因があるケースが約40%、男性由来が約25%、男女ともに原因があるものが約25%、約10%が原因不明とされています。
一方で、牛の場合、オスは種牛と呼ばれ体格の良い牛の精子の質や運動率を確認・選別し人工授精を行っています。したがって、不妊の原因の多くは雌牛にあると考えていいでしょう。
グラフは平成元年から19年までの肉牛と乳牛の受胎率の経年変化がプロットされていますが、次の3点を確認してください。

・乳牛・肉牛ともに年々受胎率が低下している
・一貫して肉牛より乳牛の方が受胎率が低い
・受胎率低下スピードも肉牛より乳牛 の方が早い
さて、この乳牛と肉牛の受胎率の違いは何が原因なのでしょうか?
重要なことなので強調しておきますが、専門家は牛の不妊の原因に氣づいています。氣づいてはいるものの、有効な解決策を提案できずに現在に至っています。
そこで、生産現場で働く獣医師がどう苦闘しているのか確認しておきましょう。
論文を一部抜粋して紹介します。
家畜の繁殖障害 星 修三 1959 年 12 巻 1 号 p. 2-7
(前略)飼育家畜の繁殖の良否は農家経営に直接影響し、とくに乳牛にあっては搾乳と関係し、一方、家畜の購入費、飼料費がますます増大する今日においては、繁殖障害はいよいよ大きな問題となっている。(中略)
家畜の繁殖は、雌雄ともに健康正常であれば、よく受胎し、生産するであろうが、そのいずれかに異常、疾患がある場合には、繁殖は障害されるのである。(中略)
乳牛にあっては、乳量の増加を図るあまり、濃厚飼料を過給し、種々の障害を起こしている場合がしばしば見られる。(中略)
過肥の場合は、脂肪が多く沈着し、繁殖力が低下することは一般に認められているところである。(中略)雄にあっては、過肥のものは精子の造成を妨げ、性欲が減退する。(以下略)
これは60年以上前‶1959年〟の論文です。この時から牛の不妊の原因がわかっていたという話です。この論文を私が要約すると次のようになります。
健康な牛なら妊娠・出産は容易なことはわかりきっている。したがって、牛に本来の餌である草を給餌したい。しかし、草を与えると乳量が減少し農家の経営が成り立たない。一方で、濃厚飼料を与えるが故の乳量増加だが、この給餌が牛を病気にして繁殖は阻害される。雄に至っては精子の形すら崩れるのがわかっているのに…。
現場で働く獣医師の苦悩を理解していただいた上で、肉牛より乳牛の不妊が多い理由を紹介します。
前述のように、乳牛はより乳量を得るため肉牛より給餌する濃厚飼料の割合が多い。一方で、そんな飼料では病気が増えて肉として出荷できないため、肉牛は乳牛より粗飼料を多くしています。
つまり、給餌される濃厚飼料がより多いことが、肉牛より乳牛の受胎率が低いこと。および、受胎率低下のペースが速いことの原因です。
繰り返しますが、牛の餌は栄養価がほとんどない草です。あの巨体がその体を維持するわけですから、牛は四六時中草を食べ続ける食性があります。また、その食性であるからこそ、濃厚飼料も食べ続けてしまうのです。
まとめ
以下の事実を強調しておきます。
不妊で、子宝に恵まれないことは残念なことです。しかし…
その原因も知らずに運よく子宝に恵まれたとしましょう。
その際、子どもを流産や早産(未熟児出産)のリスクが高くなります。また、この事実は出生児の発達障害リスクが高くなることを意味します。
一方で、妊婦は出産後の産後うつのリスクが高くなります。また、そんな母親は母性発動の低下により、育児放棄や虐待のリスクが高くなります。
この本の内容は、妊活を助けることができますが、上記のようなリスクも回避することができます。
不妊でお悩みのご夫婦にお役立ていただければ幸いです。