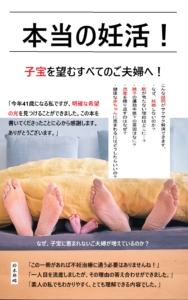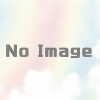赤ちゃんの細胞分裂はどうなりますか?という質問にツラツラ思っていること記します!
「赤ちゃんの細胞分裂はどうなりますか。ご教授下さい。」
「神仙堂薬局への各種お問い合わせはこちらからどうぞ。」より、こんな質問がありました。
正直、この質問では何を知りたいのか?私にはわかりませんが、細胞は分裂していません。これは、千島先生の研究から明らかです。
・血液と健康の知恵 千島喜久男著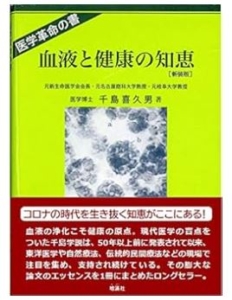 私たちが食べた物は、小腸の絨毛で赤血球となります。また、赤血球が白血球に分化し、その白血球がたどり着いた先の臓器(血管なども含め)の細胞に分化します。
私たちが食べた物は、小腸の絨毛で赤血球となります。また、赤血球が白血球に分化し、その白血球がたどり着いた先の臓器(血管なども含め)の細胞に分化します。
同様に、妊娠中のお母さんが食べたものが赤血球となり胎盤に送られます。胎盤には絨毛があることから、ここで赤ちゃんの赤血球に作り変えられ、胎児の細胞となり成長していくことになります。
このことからわかるのは、私たちの体は私たちが食べた物、そのものであること。一方で、胎児の体は、母が食べた物、そのものであることです。
病気とは?
「〇〇(例えば起立性調節障害)でした。」
不思議なことに、日本人の多くは病名を告げられると安心します。が、ヒポクラテスが「病人の概念は存在しても、病気の概念は存在しない」というように、病気は医者が作った記号にすぎません。
千島学説と病気
既述したように、食べた物が赤血球となり臓器細胞に分化(変化)します。(千島学説)
ならば、本来は食べ物であるはずもない抗生物質や農薬、薬、添加物を食せば、健康な赤血球などできるはずもありません。また、白血球が異常な免疫反応をしたり、臓器が不健康になっていくことは自然でしょう。
重要なのは、ヒトにより不健康となり不快症状が発症する部位(臓器や血管など)が違うこと。そのため、ほとんどのヒトはその不快症状が食べた物の結果だと氣づきません。
また、その無知につけこんだのが医者であり、不快症状の種類や発症部位などで「腎臓病」とか「脳梗塞」などと命名(病名をつけ)し、私たちを洗脳し続けてるのが現状です。
そして、コロナ禍で氣づき驚いたことに、西洋医学(製薬会社)は医者だけでなく他産業も使って私たちを病気に誘導していました。その最たる例が濃厚飼料(大豆やトウモロコシなど)でしょう。
脂質(油と脂)は蓄積する!
水と油。と言ったら性質が合わず、決して混ざり合わないことを指します。一方で、油は脂と馴染みます。ヒトの細胞は脂質二重層と呼ばれる脂で囲まれていますから、食べた脂質(油と脂)は人体に蓄積します。
濃厚飼料で用いられる大豆やトウモロコシは脂質が豊富に含まれます。それ故に大豆油やコーン油が食用油として用いられますが、その弊害は「卵胞の発育が悪い」「卵胞液の酸性化」「子宮への脂肪蓄積」など、少なくとも1950年代には繁殖障害が家畜で確認されていました。(過肥牛の内部生殖器変状について 岩本 研, 池本 八造 1955年 8 巻 6 号 282-284)
そしてその生殖器への弊害が飼料として給餌されている濃厚飼料にあることは、1950年代後半には専門家が指摘していました。
栄養の増進,健康の維持は生殖腺の機能を盛んにし,雄にあ っては精子の生成と交尾欲を,雌にあっては卵子の生成,卵 胞 の発育,排 卵を順調な らしめ,さ らに妊娠の継続,胎 児 の発育 にきわめて重要 な ことであ る.
家畜を飼 育す るものは,栄 養の増進 に最 も苦 心 し,努力 しているが,飼 料の選択,給 与にあた って,自 給飼料の関係 や経済的事情か ら,栄 養分 の量 と質に過不足を生じ,一 般には栄養 の不足を きたす ものが多 い.
乳 牛にあっては,乳 量 の増 加を図 るあ ま り,濃厚飼料を過給 し,種 々の障害を起 こしている場合が しば しば 見 られ る.
・家畜の繁殖障害 星 修三 1959年 12 巻 1 号 2-7 より引用
日本において大豆油やコーン油、サラダ油の普及が進んだのが1960年代からです。また、それ以降に花粉症やアトピーなど各種アレルギーが急増しました。さらに、その世代に育った子どもが親となる1990年代、食の欧米化は一般的となり日本で少子化が社会的な問題となるとともに発達障害も急増しはじめました。
このように、脂溶性である油は親から子、子から孫へと〝濃縮して″受け継がれています。
日本政府における少子化対策とは?
日本政府が掲げる少子化対策とは、文字通り「少子化にする対策」です。つまり、日本政府の思惑通り、少子化は順調に進行中しています。
また、製薬会社と医者の思惑通り順調に病気になるヒトが増えています。
繰り返しますが、私たちは食べた物、そのものです。また、子どもや孫には、食べた脂質(油や脂)は濃縮して受け継がれていきます。この負の連鎖を断ち切るには、私たちが氣づき、行動を変えることが必須であることは私が指摘するまでもありません。
オメガ6過剰摂取を断ち切る!
日本人のほとんどはオメガ6脂肪酸を過剰摂取しています。また、それにより炎症を促すプロスタグランジンが生じ、これが各種アレルギーや起立性調節障害、生殖器の障害、不妊、流産、早産などのトリガーとなっています。
低出生体重児の出生割合が高いことは我が国の将来の健康に関する問題であり,その理由の一つは妊婦のカロリー摂取量が,日本人の食事摂取基準の推定平均必要量に対して十分でないことが挙げられる.
食事に含まれる脂質はカロリーの源だけではなく,脂肪酸の系列(飽和脂肪酸,オメガ 9 脂肪酸,オメガ 6 脂肪酸,オメガ 3 脂肪酸)により,生理学的機能が大きく異なり,その例としては,
オメガ 6 脂肪酸のアラキドン酸から生合成されるプロスタグランジン類の妊婦の子宮組織での作用,胎盤を通過した後の胎児の脳などに影響を及ぼす.
オメガ 3 脂肪酸に関する妊婦を対象とした疫学研究や介入研究より,妊娠期のオメガ 3 脂肪酸摂取が早産児や低出生体重児の出産のリスクを低下させることが明らかになっている.しかしながら,近年わが国の妊娠適齢期の女性の魚介類の摂取量は低下している.
実際に,日本人妊婦の食生活パターンと Small for Gestational Age 児の出産には関連性がある.
また,周産期のうつも社会的な問題になっているが,胎児への影響を鑑み,なるべく薬物治療を避ける傾向にある.
わが国の妊婦を対象とした疫学研究において,オメガ 3 脂肪酸と魚介類の摂取量が産後うつのリスク低減と関係しているという報告がある.また,うつ病の妊婦にオメガ 3 脂肪酸を投与したところうつ尺度に有意な改善が認められている.
また,出産後に母親が摂取した脂肪酸が母乳の脂肪酸組成に影響する.近年の日本人母乳の DHA 含量はかつてのレベルより少なくなっている.
周産期における脂肪酸の栄養学的重要性 押田 恭一 2022年 10 巻 2 号 28- より引用
さらに、うつ病など精神疾患のトリガーとなります。不安障害やパニック障害なども、サラダ油や植物油脂、トランス脂肪酸を使った調理や加工食品の摂取が主要因であることを再認識してください。
アラキドン酸代謝経路により産生される炎症性エイコサノイドは子宮頸管熟化や子宮収縮を誘導して分娩進行を司る中心的因子である。
早産の背景原因は多岐にわたるが、最終的にはそれらの炎症性エイコサノイドの異常な活性化による妊娠維持機構の破綻が生じて分娩となる。(中略)
炎症性プロスタグランジン(PG)の中で PGE2 やPGF 2αは分娩進行に関わる中心的な脂質メディエーターであり、人工的に分娩を誘導する処置である分娩誘発では、頸管熟化および子宮収縮の促進を目的として、炎症性 PGの投与が行われる。
これらの炎症性 PG はオメガ 6PUFAs であるアラキドン酸を起点とした代謝経路により産生され、アラキドン酸カスケードと称される。
子宮の炎症制御における脂質メディエーターの役割 ―オメガ3脂肪酸を中心に 永松 健 2022年 31 巻 1 号 30-35 より引用
腸内細菌は重要である。
この事実に異論を持つヒトはいないと思いますが、重要な事実として食べた脂質は腸内細菌も利用しています。
ここでは詳細を避けますが、千島喜久男先生は細菌が自然発生するという事実も発見しています。納豆から納豆菌が、乳製品から乳酸菌が発生します。また、肺には肺炎菌、腸には赤痢菌やチフス菌が発生します。
これらことから、培地と状況(食べた物や体の汚れ)という状況により体に有用な菌が発生することもある一方で、有害な菌が発生すること示唆しています。
これまでは、医学的ハイリスクへの予防治療が主だったが、現在はローリスクも含めた早産予防が注目されており、Prebiotics、Probiotics、オメガ3脂肪酸などがある。
Prebioticsは、食物繊維やオリゴ糖など腸内細菌などによい影響をもたらす食品で、Prebioticsのひとつであるラクトフェリンは、抗菌作用や抗炎症作用を有し、早産動物モデルや難治性細菌性膣炎症例(ヒト)において、早産予防効果があると報告されている。
Probioticsは、乳酸菌などの生体、特に消化管へ有益に働く生菌で、早産ハイリスク妊婦における膣内細菌叢の変化による子宮内感染の低減や、全身の抗炎症作用による早産予防が期待されている。
早産ハイリスク妊婦に活性生菌製剤(Probiotics)を投与したところ、32週未満の早産と絨毛膜羊膜炎が有意に減少したと報告されている。
また、エコチル調査からの報告では、妊娠前に発酵食品(味噌汁やヨーグルト、納豆)を摂取するように心がけていた人は早期早産のリスクが低かった。
オメガ3脂肪酸は、小型魚類やえごま油などに多く含まれる多価不飽和脂肪酸で、エイコサペンタエン酸(EPA)やドコサヘキサエン酸(DHA)に代表され、その代謝物質は抗炎症作用を有する。
LPS誘導早産マウスモデルでオメガ3脂肪酸は早産を減少させたと報告されている。
また、特定臨床研究において、頸管長短縮を生じた妊婦にオメガ3脂肪酸内服したところ、早産率を低下する効果が示された。
早産児の後遺症なき生存を目指して 米田 徳子 2022年 57 巻 4 号 581-585 より引用
つまり、食べ物ではないものを食べれば腸内で悪玉菌が増え、適切な物を食べれば有用菌(俗に言う善玉菌)が増えます。前者が有害物質を、後者が私たちの健康に寄与する物質を生じさせることになるという事実も忘れないでください。
まとめ
私がオメガ6脂肪酸の過剰摂取かつオメガ3脂肪酸の摂取不足を指摘するようになって、19年経過しました。
そのきっかけは朝起きられない病気、起立性調節障害の相談でした。
・30日で朝「スッキリ目覚める」体質にする方法!: もう、起立性調節障害で悩む必要はありません。
また、上記著書により起立性調節障害の相談が急増すると、そのご家族のほとんどが大きな問題を抱えていることに氣づきました。例えば、子どもが起立性調節障害だと、本人はもちろん、ご両親のほとんどが鼻炎や花粉症などのアレルギーを発症していること。また、母親のほとんどが足が浮腫むこと。さらに、母親の一定割合がご主人のモラハラで悩んでいたことです。
・30日で足が「むくまない体質」にする方法!: 「生活の質を高める実践栄養学」がすすめる足の浮腫み解消法とは?
さらにさらに…
当時、起立性調節障害を克服した子どもの多くはすでに結婚していますが、それが女性の場合は食事の重要性を理解し10日間チャレンジを実践している一方で、男性の場合は結婚した女性次第で食生活が変わります。また、後者の場合、その多くが不妊で悩んでいることに氣づき「本当の妊活!」を執筆しました。
リセットは秒読み段階に入ったようです。
これから大きな変革が起きますが、このピンチをチャンスに変えることができるよう努めてください。そしてそれには、食生活の改善が最優先であることを忘れないでください。